「追求」で変わりゆく地球に適応! ハワイで見つけたコーヒーの未来。
「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、独自のサスティナビリティ活動をグローバルに展開している「UCC上島珈琲」。1980年代にジャマイカとハワイにコーヒーの直営農園を開設し、生産地で自らコーヒーを育てながら、コーヒー農家の労働環境の向上や森林保全に寄与する活動を長年続けています。近年、コーヒー農園として世界で2例目、日本企業では初となるGLOBAL G.A.P.(Good Agricultural Practices:適正な農業実践)認証を取得したハワイ島の「UCCハワイコナコーヒー直営農園」を訪ねました。
コーヒーの栽培地が半減する!? 深刻な「コーヒー2050年問題」
「30年後にはコーヒーが飲めなくなるかもしれない」。そんな噂を耳にしました。
私は取り立てて、「コーヒーが大好き」というわけではありません。それでも仕事の打ち合わせや空き時間に「コーヒーでも」という流れになることも多々。1杯も飲まない日もありますが、それでも平均すると1日2杯は飲んでいるんじゃないかと思います。
一方で、私たちは「コーヒー2050年問題」に直面しています。地球温暖化は、農作物であるコーヒーの栽培にも大きな影響を及ぼしています。たとえば、気温や湿度の上昇により「さび病」というコーヒーにとって深刻な病気が発生しやすくなり、収穫量の減少や、品質低下を招くことが懸念されています。現在、南緯25度から北緯25度がコーヒーベルト(コーヒーの栽培地)とされていますが、国際調査機関のワールド・コーヒー・リサーチでは、2050年には飲用に栽培されるコーヒー品種の主体を占めるアラビカ種の栽培地が75%も減少するという報告がされています。
そんな折、UCC上島珈琲が運営する「UCCハワイコナコーヒー直営農園」を取材しないかという誘いを受け、なかば食い気味に快諾! 同農園では、「コーヒー2050年問題」を見据えてサステナビリティに注力しながらコーヒーづくりをおこなっているのだとか。ぜひこの目でたしかめてみたいと、ハワイ島へ向かいました。

コーヒー豆(生豆)とは、アカネ科コフィア属に分類されるコーヒーの木の果実から取り出された種子のこと。果実の中には、薄皮に包まれた2粒コーヒーの豆が入っています(稀に3粒の場合もあり)。写真/長谷川あや
青い空と海。絶景を見下ろすコーヒー農園
「UCCハワイコナコーヒー直営農園」は、ハワイ島西部のコナ地区のフアアライ山の裾野にあります。中心地から車で15分ほどですが、標高は約460m。裾野とはいえ、ちょっとした高台です。
この日、案内してくれたのは、同農園の運営の先頭に立っている小林司さん。「いきなり標高が上がるので、耳が痛くなってしまう方もいらっしゃるんですよ」。小林さんが言うように、農園はホテルが建ち並ぶビーチエリアよりぐんと高い位置にあり、コーヒー畑の向こうにはコナの街とアクアブルーの海が一望できます。

写真提供/UCC
「この景色を眺めながら飲むコナコーヒーが最高なんです」と小林さんは目を細めます。たしかに息をのむほどの絶景! そして、“コーヒーの木と海”という、私の約半世紀の人生において初めて観る景色をしばし茫然と眺めていました。
小林さんによれば、この標高の高さがコーヒーづくりに適しているとのこと。なるほど、だから一帯はコーヒー農場ばかりなんだ。コーヒー好きの方はいくつかの農園をはしごするという話も聞き、「そんな世界があったとは!」とこれまた驚きでした。

ハワイコナコーヒーとは、“ハワイ島の西側のコナ地区で栽培されるアラビカ種のコーヒー”のこと。やわらかな酸味と滑らかな口当たりが特徴です。年間の生産量は1000~1500トンと、世界のコーヒー生産量の0.05%未満。希少価値が高く、必然的に高価になります。写真提供/UCC
コーヒー畑の見学に訪れる人たちが続々

現在の農園の総面積は約16ヘクタール(東京ドーム約2個分)、うち植付面積は約9ヘクタール(東京ドーム約3.5個分)ほど。畑は標高260mから450mにおよび、コーヒーの2大品種のひとつであるアラビカ種に属し、ハワイの伝統品種でもあるティピカ種を中心に、1万8000本あまりを栽培 写真提供/UCC
「UCCハワイコナコーヒー直営農園」もビジターを積極的に受け入れていて、この日もクルーズ船でハワイ島に寄港している人たちが代わるがわる立ち寄っていました。畑の一部を開放していて、コーヒーの木のかなり近くまで行けるのもうれしいポイント。日本語で説明を受けられるのも心強いです(笑)。
ショップではコーヒーや、コーヒーを使ったお菓子も販売しており、コナコーヒーの焙煎体験もできます。小林さんが「ぜひ食べてください! ダントツ人気の商品です」と勧めてくれたのはアフォガード。

写真/長谷川あや
農園で採れた豆をつかってつくったアイスクリームと、コナコーヒーのエスプレッソを合わせたアフォガードは、すっきりした苦みと甘み、酸味とが見事に交錯した大人のデザート。一番人気なのも納得。これはクセになります。
自社農園でのコーヒー豆の生産量はごくわずか
UCC上島珈琲が直営農園をハワイ島に開園したのは1989年のこと。1981年にオープンしたジャマイカのブルーマウンテンエリアの農園に次ぐ、2つめの直営農園として誕生しました。
日本の立地が「コーヒーベルト」から外れていることもあり、日本の多くのコーヒーメーカーは、海外の契約農家からコーヒー豆を輸入しています。UCC上島珈琲のように海外に自社農園を持つメーカーもありますが、その流通量はごくわずか。
コナ地域では中規模以上の「UCCハワイコナコーヒー直営農園」でも、生産量は年間わずか4.6トン(麻袋で100袋ほど)です。それでも自社農園を持つのは、なぜなのでしょうか。
「UCC直営農園は、“栽培段階から品質を追求する”という意味合いが強いですね。“気候変動対策や循環型農業に実験的にチャレンジする”拠点として位置づけられています」
そのため、農園のショップとECで購入できますが、日本に住む方々の口に入ることは稀です。2024年9月に、UCCオンラインショップでコナコーヒーの取り扱いがスタートした際は、コーヒーラバーの間でちょっとしたどよめきが起こったそう(笑)。

収穫したコーヒーの実の外側の部分を取り除き、焙煎前の生豆(なままめ)と呼ばれる状態にする工程のことを精製と呼びます。精製の方法はさまざまで、コナ地域では、水洗式(ウォッシュド)が一般的ですが、現在「UCCハワイコナコーヒー直営農園」では、酸素のない状態で、酵母で発酵させる嫌気性発酵に取り組んでいます 写真/長谷川あや
地球温暖化で収穫の時期が早まっている
「UCCハワイコナコーヒー直営農園」では、いったいどんな取り組みをしているのか。具体的な内容を小林さんに教えてもらいました。
「いろいろな取り組みを行っていますが、まずはわかりやすいところからお伝えすると、畑から出る残渣(ざんさ)を堆肥(たいひ)にし、畑に戻す循環型農業に取り組んでいます」
コーヒー豆は、コーヒーの果実(コーヒーチェリー)の種子を焙煎したもの。その種子以外の部分や生産量向上のための伐採(生長を促すため、地表から30㎝残し木を伐り更新させているそうです)で出る木をチップにして、肥料として活用しています。
「地球温暖化により年々、収穫の時期が早まっています。10年前は8月スタートでしたが、2024年は6月末から収穫を行っています。あまりに暑くなることはコーヒーにとってもいいことではありません。そこで、コーヒーの木に強い日差しが当たることを防ぐため、アフリカンマホガニーやグラビリアなど、背の高い木を植えて木陰を作っています。気候変動がもたらす病虫害の対策として接ぎ木も行っています」
病害虫に耐性のあるリベリカ種に、デリケートなアラビカ種を接ぎ木することで、生産性が上がるのだとか。

収穫は実が赤くなってから。「コーヒーはフルーツですから、赤く成熟したもののほうがおいしく仕上がります」(小林さん)。同じ木でも実の熟すタイミングが異なるので、6月末から12月くらいまで約半年をかけて収穫をしているそう 写真/長谷川あや
そしていま農園で絶賛推進中なのが、計画的なコーヒーの木の植え換え作業。
「コーヒーの木の寿命は一般的に20~30年とされていますが、農園には1989年の開園時に植えられた木も多く残っています。30年を超え、収穫量も落ちているため、標高の低い下のエリアから、老木を若木に植え換えていくことにしました。20年をかけて、農園の約1.8万本の木すべてを若木に置き換えていきます」
区間ごとに植替えていくという計画ですが、そもそもハワイ島は海底火山の火山活動で形成された溶岩島。農園の土にもたくさんの溶岩が混ざっています。ミネラルを多く含む溶岩台地は、水はけもよく、コナコーヒーの味わいにはプラスに働いているといわれているのですが、硬くて厚い溶岩岩はコーヒーの木そのものにとっては根を伸ばせず、実はやっかい。そこで、植え換えのタイミングに合わせて溶岩を取り除く大規模な土壌改良を実施。畑の横には取り出した溶岩が高く積まれていました。

写真/長谷川あや

写真/長谷川あや
新しい技術を他の農園に共有することも
農園を歩きながら、小林さんはこんな話もしてくれました。
「きちんと収入を得て生活を向上させるサイクルのなかで、環境負荷の少ない農業を提案したり、新しい技術を共有したりと、直営農園には、ここで得た知見を他の農園に広げる役割があるんです」
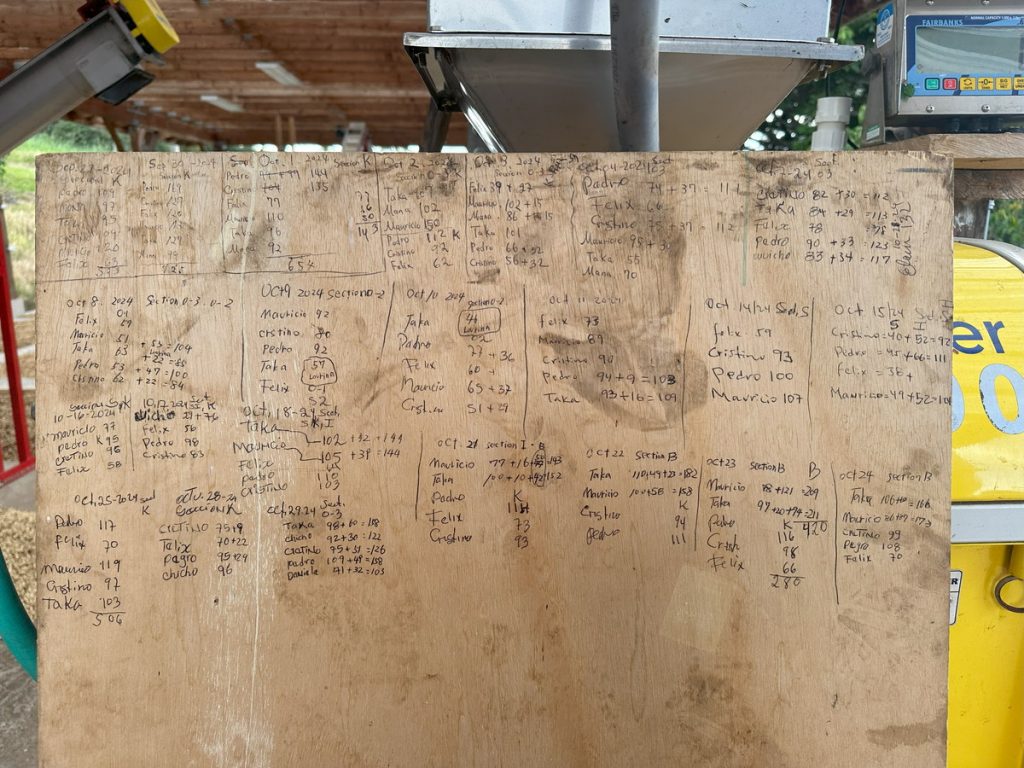
農園としてより多くのコーヒーを収穫できるように試行錯誤を繰り返すことも大切なので、最先端の技術を取り入れながら、日々コーヒー栽培に関するデータ収集などもおこなっています。写真/長谷川あや
ふと顔を上げると、真っ赤なコーヒチェリーをたたえるコーヒーの木々は、青く輝く海を背負って悠々と溶岩島の大地に根をおろしていました。そんな風景のなかで小林さんの力強い言葉を聞いていると、「コーヒーの未来は決して悪いものではない」という思いが沸き上がってきます。
リラックスするためにコーヒーを飲むとき、できれば難しいことは考えたくありません。ただ、「このコーヒーはどこから来たのかな」と、その壮大な旅路にほんの少し思いをはせることはあると思います。そしてその思いが、「コーヒー2050年問題」を少しでもよい方向に変えていくことにつながっていくかもしれない。
今回のハワイ島では、商品を手に取る前に、モノづくりの背景やつくり手の思いを知ることの大切さも感じました。これは私たち買い手、つかい手にもできる環境や人に配慮したアクションですよね。知っているからこそ、モノへの向き合い方がよりよい方向へと変わり、さまざまな気づきやポジティブな変化をもたらしてくれるのだと思います。

写真提供/UCC
取材・文/長谷川あや



![[コーヒー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_coffee.svg)
![[企業]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_company.svg)
![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)
![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)





![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)
![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)

![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[環境]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_environment.svg)

![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)

