みちのく“食”の物語【第2回】 東京からUターン!秋田の郷土食「いぶりがっこ」を“土からつくる”農家の5代目
2025年1月、日本橋三越本店で行われたご飯の“お供”ばかりを集めた物産展『食のなんじゃこりゃ〜博覧会』。その一角に、みちのくのおいしいものが集結した「東北笑福市」がありました。おいしいおかずが並ぶなか、多くの人が魅了されていたのが、秋田名産の「いぶりがっこ」。土づくり、大根栽培からこだわって生産している田口悦章(よしあき)さんに、地域の農家の現状やこだわりなどを聞きました。
農薬も化学肥料も不使用。土づくりからこだわる「いぶりだいこん」
いぶりがっこは、大根を燻(いぶ)して漬け込んだ秋田県発祥の漬物。冬に稼ぐのが難しいという秋田で、ダイコンを燻製して保存食に加工したのが始まりだという。ふつうのたくわん漬けとはまた違う味わいで、燻製香がなんともクセになる、ごはんのお供だ。
秋田県大仙市出身の田口さんにとって、いぶりがっこは小さいころから慣れ親しんできた“郷土の味”だ。4代続く農家で生まれ育った田口さんは高校を卒業後、あこがれの地、東京で専門学校に入学。卒業後はさまざまな職種を経験し、不動産会社の営業として働いていた際に、ふと我に返ったと話す。
「リーマンショックが起きた直後で仕事も厳しく、心に余裕がなくなっていたんでしょうね。食事といえば、定食屋やファミレス、コンビニのお弁当ばかり。そんなある日、ひとりで『今日は何を食べようかな……』と考えていたら、突然涙が出て止まらなくなったんです。『何で、こんなに悲しいんだろう』と理由を探ってみたところ、自分の身体をつくっている食べものをおろそかにしているからじゃないか、と気づきました。さらに、人口増加に伴う世界的な食糧危機についての記事を読んで、『食べものが自分のキーワードになるのではないか』と思いいたったのです」(田口さん、以下同)
そこで一念発起。埼玉県比企郡小川町で有機栽培に取り組む「久野農園」の門を叩き、有機農法を学ぶことにする。そこで園主の久野裕一さんから、農法だけでなくさまざまなことを学んだ。
「あるとき師匠に、『悦章は何のために農業をするの?』と聞かれて、『生きていくためです』と答えたんですよ。そうしたら、『誰々に食べさせたいっていう想いはないの? おいしい野菜をどんなにつくっても、食べてもらえなかったら意味がないでしょう』と言われたんです。そこで、食べる相手を想像することの大切さに気づきました」

原料となる大根は、土づくりからこだわって自ら栽培する
自然と触れ合ううち、いろんな真理に気づいた
「久野農園」には、有機農法に挑む多くの生産者が訪れるという。田口さんはそんな全国の農家からも、さまざまな学びを得た。
「月の満ち欠けに合わせて農業をする人や、微生物を研究して畑に活用する人、肥料も何もつかわずに奇跡のリンゴをつくる人たちと話をするうちに、農業って面白い!と気づいたんです」
実際に土と触れ合い、野菜を育てていると『自分に大切なことは、じつはすぐそばにある』と実感できた。そんなとき、秋田の父親が血液のガンにかかってしまったのだ。
「秋田に戻って、久野農園で教わった有機農法でダイコンを育てて、商品名『いぶりだいこん』の生産を始めたんです。あんなに避けてきた実家の家業を、次男である自分が(5代目として)継ぐことになるなんて!」

収穫した大根を木製の梁(はり)に並べ、桜の木で3日間ほど燻製。その後、砂糖と塩、米糠で漬けこみ、発酵熟成させる。これらを、すべて手作業でおこなう
地元で「いぶりだいこん」をつくりながら思うのは、「人口減少が進む秋田を、農業と食品加工業から元気にしたい!」ということ。周辺に空き家が増え続けていることに、心を痛めている。
「空き家を移住者に向けて改修したくても、所有者が県外や高齢者施設にいて、なかなか手を出せないんです。解体するのも大変で、キツネやイタチに荒らされてしまう。住むところがあるのに、人が住めないのは歯がゆいですよね。秋田は人口の減少率が全国1位で、同世代の仲間の多くは県外に出ている。このままだと、日本の地方はスカスカになってしまいます。すると税収も減って自治体も先細りになっていくでしょう。生活ができないから、残る人がますます少なくなる。何とかしなければ、と強く思います」

いぶりがっこは、いまや全国区。催事で田口さんが「いぶりだいこんは無添加で、農薬をつかわずにつくっているんですよ」と説明すると、多くの来場者が興味を示していた

田口さんが手塩にかけてつくる、いぶりだいこん。「チーズに味噌、マヨネーズにも合いますよ。ポテトサラダに入れてもすごくおいしい。海外の方にもぜひ味わってもらい、日本にも燻製文化があることを知ってもらいたいです」
秋田には伸びしろがいっぱいある、と田口さん。生活できるだけの収入さえ確保できれば、とても豊かに暮らせるというのだ。
「東京に住んでいたときは、いつも自然に飢えていた気がします。部屋に観葉植物を置いたり、公園に散歩にいったりして自然を取り込んでいました。秋田には無尽蔵にありますからね(笑)。スキーやスノボなどのウィンタースポーツや温泉も、とても身近です。ただ、秋田人は口数が少なく、コミュニケーションが不得手だな、と感じます。『アレあるじゃん』と言われても、『アレじゃわかんないよ』と思うことがよくある。市民と自治体の人たちとの連帯感が薄いのは、そこに原因があるんじゃないかな」
田口さんは、地方の問題の多くは現場にあると考えている。
「ですから自治体の方々には実際に農作業をしてもらい、現場を知ってもらいたい。現場に、何かしらの改善策があるんですよ。山に雨が降ると川になって海に流れていく。里山の農業は海とつながっているんですよね。漁師さんと手を組んで、何かできることがあるかもしれない。そんな循環を肌で感じてもらえるように、多くの人とコミュニケーションを深めていきたいと思っています」
Photo:横江淳(催事場での田口さん) Text:萩原はるな



![[地域]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_region.svg)
![[食べること]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_food.svg)
![[インタビュー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_interview.svg)





![[トピックス]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_topics.svg)
![[くらし]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_life.svg)

![[カルチャー]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_culture.svg)
![[旅]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_journey.svg)

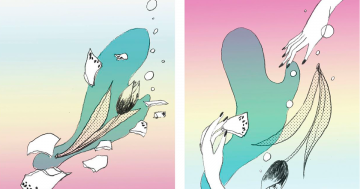
![[人権]](https://dowellbydoinggood.jp/wp-content/themes/dowell/img/common/articletag-tag_human-rights.svg)


